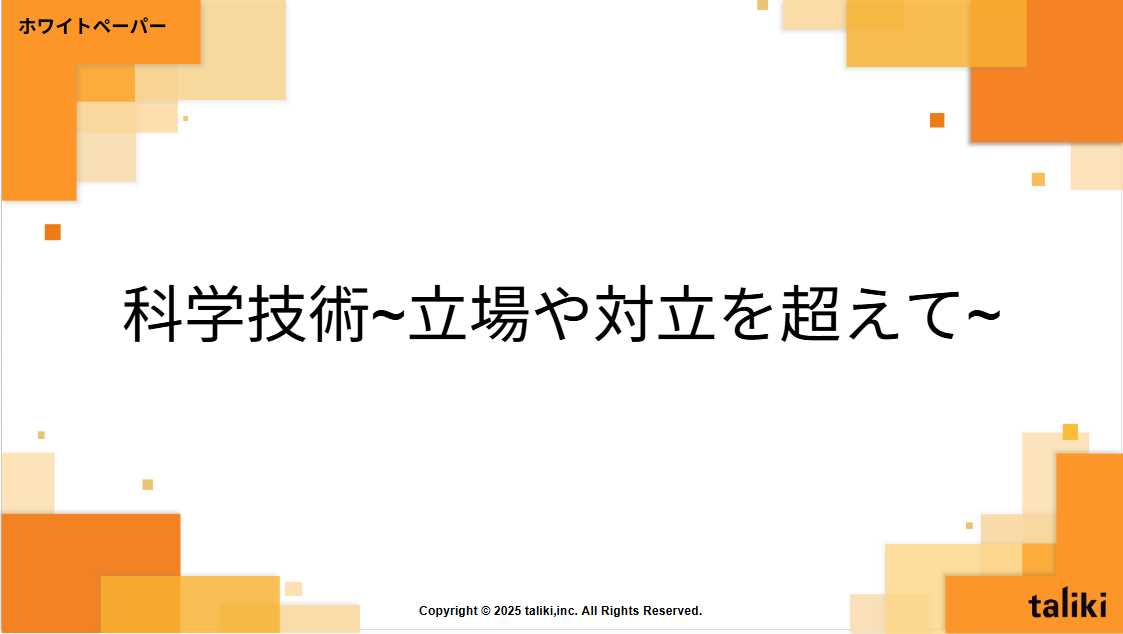人の死という語られてこなかった領域へ、ビジネスで挑戦する。
医療の発達やお葬式のあり方の変化によって、人の死を社会から遠ざけることに成功した。改めて人の死に向き合うお葬式の意味が問い直されている。「変化にもっと優しく」というビジョンを掲げ、人の命を含む、全てのものが終わりという変化を迎えるという、いわゆる”無常観”を社会に取り戻そうと取り組む、株式会社むじょう。デジタルで新たな弔いの場所を作る『葬想式』や、本物の棺桶に入って自分の死を擬似体験できる『棺桶写真館』など、事業や実験的な企画を立ち上げてきた。CEOを務める前田陽汰に、今の社会への課題意識や、前例のない領域に株式会社として挑戦する理由などを聞いた。
【プロフィール】前田 陽汰(まえだ ひなた)
株式会社むじょうCEO。2000年生まれ。中学卒業までは東京都杉並区で過ごし、釣り好きが高じて、島根県の隠岐郡海士町の高校に進学。海士町での経験から、経済成長や人口増加といった右肩上がりが前提とされ、終わりゆくものがタブー視される社会に違和感を持つようになる。2019年に慶應義塾大学総合政策学部に進学。2020年、株式会社むじょうを設立。
もくじ
人の死や終わりゆく万物にも、温かい目を向けられる社会へ
ー株式会社むじょうで掲げられているビジョンは、成長を目指すベンチャー企業にはあまりない考え方に基づいているように思いました。まず初めに、ビジョンについて詳しく教えてください。
ビジョンとして「変化にもっと優しく」を掲げています。周りのベンチャーやスタートアップは新しい価値の創造を目指していますし、社会全体で経済成長や右肩上がりが前提にされていると思います。一方で新しいものが出てくる時に、役割を果たしたものや古いものが淘汰されていくのは当たり前のことだと思います。そういった淘汰されていくものに優しい眼差しが向けられない状態に課題を感じています。会社名の元にもなっている“無常観”を取り戻し、良い状態も苦しい状態も続かないという当たり前のことを認識し直して、終わりゆくものにも温かい目を向けられる社会のために事業や企画に取り組んでいます。
きっかけは高校時代を過ごした隠岐での経験です。人口が減り、10年後の存続が確約されないような集落に身を置いてきました。そこで“地方創生”という掛け声のもと終わりに抗う風潮に違和感を持ったことが課題意識のきっかけになっています。そこから、NPO法人ムラツムギを立ち上げて“まちの終活”の事業に取り組んできたのですが、より根本的に、人の命の終わりを起点に取り組みたいと思い株式会社むじょうを立ち上げました。終わりへのタブーは人間が死を日常から排除することに成功した頃から強まってきたと考えています。誰しも命に限りがあるということを、強い実感を持って意識できていない中で、例えば親が亡くなった時に「もっと親孝行をしておけば良かった」と悔やみます。その1つの原因は葬儀のあり方が変わってきた*ことが大きいと考えています。戦後間もない頃は人が亡くなると地域の“葬式組”が活躍しました。ご近所さんが亡くなったらお葬式を手伝って、地縁の中で送り出していこうというやり方で、日常的に人が亡くなるのを目にするわけです。やがて、葬祭業者がお葬式を商品として扱うようになると、生活の中で人の死に出会う機会が減っていきました。見えづらくなった人の死について段々分からなくなり、人生に死という締め切りがあることすらも分からないという状況が生まれてきたのだと考えています。
*碑文谷創の葬送基礎講座22 葬祭業はどう変化してきたか? 戦後葬儀の歴史(上)
 株式会社むじょうのビジョン「変化にもっと優しく」
株式会社むじょうのビジョン「変化にもっと優しく」
ー株式会社の形を選ばれた理由を教えてください。
NPO法人ムラツムギとは性質を分けた事業を行うためです。ムラツムギは、普段は公務員として働きながら関わってくれているメンバーが多く、細く長く啓蒙し続ける体制でいたいと考えています。定期的なカンファレンスを開催するような活動を軸に、少しずつノウハウが溜まっていくのが理想ですね。一方むじょうではよりダイナミックに実験的な内容を扱っていますし、私自身の思想が濃く出ているので、本職のあるメンバーが多い団体でそれをやるのはリスクが高いと思っています。根本のビジョンは「変化に優しく」というもので同じなのですが、アプローチの内容を変えているということですね。それに、むじょうでは仮説検証のサイクルを早く回すために、資金調達のスキームが多様な、株式会社の形でやっています。
お葬式に行けない人にも、デジタルで弔いの場を
ー次に具体的な事業の内容について伺います。まず『葬想式』について教えてください。
葬想式はスマホで偲ぶ会を開催できるオンライン追悼サービスです。参列者は思い出の写真やメッセージを共有でき、ご親族はご自身がお持ちでない、故人様の写真を受け取ることができます。着想のきっかけは自分の祖父が亡くなった時に、お葬式の役割について問い直したことと、その後のコロナ禍で満足にお別れができなかった人の想いの行き場について考えたことでした。

祖父が亡くなったのは2020年の1月で、コロナ禍前だったので、一般葬で執り行うことができました。人が亡くなった時には悲しい感情が真っ先にやってきますが、お葬式が足場になって、自分の感情に対してまた違う見え方がするんですよね。例えば思い出コーナーで私が生まれる前の祖父の写真を初めて見ました。私の知らなかった祖父の生き方を知ることで、自分がこれからどう生きるのかを考える機会になりました。人が死んでしまったらそれ以上思い出はできないと思っていましたが、お葬式を通じて新しい思い出ができたという経験だったんです。お葬式は悲しみ以外の感情にも目が届くようにサポートしてくれる“感情を見渡す足場”としての役割を持っているのではないかと仮説を持つようになりました。
その後コロナ禍で、お葬式がさらに小規模化するといった状況になったんです。祖父のお葬式以降、日本の葬送習俗の歴史について関心を持つようになり、古典的な葬儀に関する本を読んで勉強してきた私は、この状況が歴史上例のない状況だと思いました。ごく一部の親族のみがお別れし、それ以外の人々の多くがお別れを諦めざるを得ない状況って今までなかったんですよね。お葬式に行けない人たちが、故人とお別れをしたり、自身の感情を見渡して気持ちを昇華する場所を作りたいという願いが私の中で生まれました。お葬式に代わる何かをつくることはできませんが、お葬式に行ける・行けないの間を作ることはできると思ったんです。例えば、インターネットの強みを活かした思い出コーナーを作ることはできるのではないかと。それで2020年の3月に葬想式の構想をはじめ、7月にβ版をリリースしました。
ーどのような流れで利用できるのでしょうか?
葬想式のサイトにアクセスしていただき、利用登録ボタンから、簡単にご利用いただくことができます。アプリのインストールなどは不要です。利用登録の時点で、いつ開式するかを選択できるので、四十九日や命日、故人様のお誕生日などに併せて開式される方が多いです。スマートフォンの操作が不慣れな方の場合、お電話で開式のサポートをする場合もありますし、ご高齢の方で「全く分からないけどとにかく式を開きたい」とおっしゃる場合はご自宅まで伺って、一緒に操作をやりながら開式まで進めていきます。もちろんご自身で利用登録をされて、特に相談することもなく利用されることもありますね。
ー利用者の方は、どんな属性の方がいらっしゃるのでしょうか?
お子様をなくされた親御さんが開式されることが多いです。お子様のお友達のうち1人に、「葬想式を開催するから他の人にも教えてあげて」と伝えると、友達の間で拡散されて100人くらいの参列者が集まることもあります。若い方だと、友達と遊びに行っている時の写真を親に共有したりすることって少ないじゃないですか。特に若い男の子だと、友達から送られてくる写真を通して息子さんの新しい一面を見られることもあって、「新しい思い出ができました」という声をいただくこともあります。それから、ご友人を亡くした方が利用されることもあります。ある方は大学の研究室の同期が亡くなり、ご遺族の方から他の知人にも訃報を伝えて欲しいと伝言されたということで。ただ亡くなったということを伝えるだけだと実感を持つこともできず寂しいので、何かできることがないかと考えていた時に葬想式を見つけて、友達同士で偲ぶ会を開きたいと相談してきてくださいました。お葬式に参列してお別れができない時に、その人が亡くなったと実感をするには何らかのアクションをする必要がありますよね。例えば生きている人とも会うことがなく、連絡も取らなければ、亡くなっているのと同じ状態じゃないですか。葬想式をきっかけにカメラロールを遡り、その人が亡くなったということを自分の中で反芻しながらメッセージを書くという営みがあることによって、葬式には行けないけれどお別れすることができたという声もいただいています。
葬想式に集った人が、日常に還っていけるように
ー葬想式のサービス実装をする上で、機能やデザインの面でこだわったのはどんなところですか?
UXは特にこだわっています。例えば、葬想式を開催してから3日で集まったメッセージや写真は消えてしまうようになっています。残念がられる方もいるのですが、デジタルは劣化せず100%そのままの画像を残せてしまうので、葬想式を卒業できないということになってしまうかもしれません。身近な人を亡くしてその人がいない日常に戻っていく必要があるのに、葬想式が日常に戻らないでいるための拠り所になってしまってはいけません。将来的にサイトを保持できるようにすることも検討していますが、デジタルでも何らかの時間経過を感じられる要素を付与したいと思っています。「経年劣化するデジタル」というイメージです。それから、どの世代の方でも直感的に使えるということも大事にしていて、テストでは50〜60代の方に使ってもらい、手元を撮影させていただきどこでつまづくか観察しています。

ーユーザーの満足度を測る指標として、何を用いていますか?
ユーザーの満足度を測る段階にはまだ行けていないと思っているので、指標は設けていません。というのも、お葬式というのはあまり複数回やるものではないですし、比較することが難しいんですよね。初めての経験である以上、ユーザーに聞いてもほとんどは「よかった」という感想になるので、あまり参考になりません。今は満足度を測るよりもどの体験が良かったのかを測るようにしていて、例えば写真を1枚共有する上でもキャプションの有無、写真を送った人が分かるかどうかといった細かい部分の最適化をするようにしています。
ー他に、サービス運営の上でどのように仮説検証を進めていますか?
葬想式を通じて検証したいのは、「葬想式は血縁を越えられるか」ということです。人の死というのは親族の間で“私有化”されていて、血縁がないと弔うこともできないような状況があります。お墓参りに行くのは遺族に申し出ないといけないという慣習があったり、お葬式は遺族が喪主になって開式することになっていたりしますよね。でも例えば年に1度しか会わない遠い親戚と、週に1度は会う友人と、どちらと関係が強いかといえば優劣は付けられないと思います。このように血縁に限らず友人にも弔う権利があることを謳った上で、友人主催の葬想式がどれくらい立ち上がってくるのかといったことは仮説検証で重視しているところです。
自身の死について考えることが、生き切ることにつながる
ー不定期で開催されている、『棺桶写真館』について教えてください。
まだ始まったばかりで形を変えながらやっているんですが、初めは渋谷の雑居ビルを借りて、そこに棺桶を設置して開催しました。棺桶写真館ののれんをくぐってビルの一室に入ると棺桶の設置された“死の間”になっていて、遺書を書いて棺桶に入るという体験ができるようになっています。1人で来た人には遺書を書いた後に棺桶に入ってもらい、「安らかにお眠りください」と呼びかけて棺桶の蓋を閉め、5分間過ごしてもらいます。家族やカップルで来ている人たちには、「パートナーや家族が本当に亡くなってしまったと思って蓋を閉めてあげてください」と呼びかけます。家族やパートナーに見られながら棺桶に入る場合、他者との関係性の中で自分の死を位置付けることになり、「自分が死んだらこの人はこんな感じで悲しむのか」といったことを考える時間になります。蓋を閉める側の人としては「パートナー/家族が死んでしまったらこんな気持ちなんだ」といったことを体験していただけます。本物の棺桶を使っているので本当にリアルな体験で、「死を意識した」「いつか死ぬという当たり前のことに気づいた」といった声をいただいています。
葬想式で対象にしているのが自分以外の人の死、すなわち“二人称の死”なのに対し、棺桶写真館は自分自身の死、すなわち“一人称の死”について考えてもらうというコンセプトがあります。この体験は自分の生命を生き切ろうとするきっかけになり得るんですよね。いつか自分も死ぬという当たり前のことを実感することで、日々の過ごし方が変わるはず。締め切りがあるから頑張れるというようなことが人間には結構あると思います。このような仮説があり、棺桶写真館では「死を生に活かすことはできるのではないか」という仮説を持って取り組んでいます。
ー最後に、今後事業をどんな領域に進めていきたいか教えてください。
将来的には人の死についての事業だけにこだわる必要はないと思っています。「変化にもっと優しく」というビジョンの中で、事業の撤退という終わりや、家を手放すという終わりなど、色々なものの終わりに優しい眼差しを向けてソフトランディングできる選択肢を作っていきたいと思っています。とはいえ、当面は人の死に対して「死の私有化の解体」をメインテーマに、葬想式を作り込んでいくつもりです。

株式会社むじょう https://www.mujo.page/
棺桶写真館 https://www.mujo.page/kanokeshasinkan
公式note https://note.com/mujo_info/
interviewer
細川ひかり
生粋の香川県民。ついにうどんを打てるようになった。大学では持続可能な地域経営について勉強しています。
writer
掛川悠矢
記事を書いて社会起業家を応援したい大学生。サウナにハマっていて、将来は自宅にサウナを置きたいと思っている。
関連する記事
社会課題に取り組む起業家のこだわりを届ける。
ソーシャルビジネスの最新情報が届くtalikiのメルマガに登録しませんか?