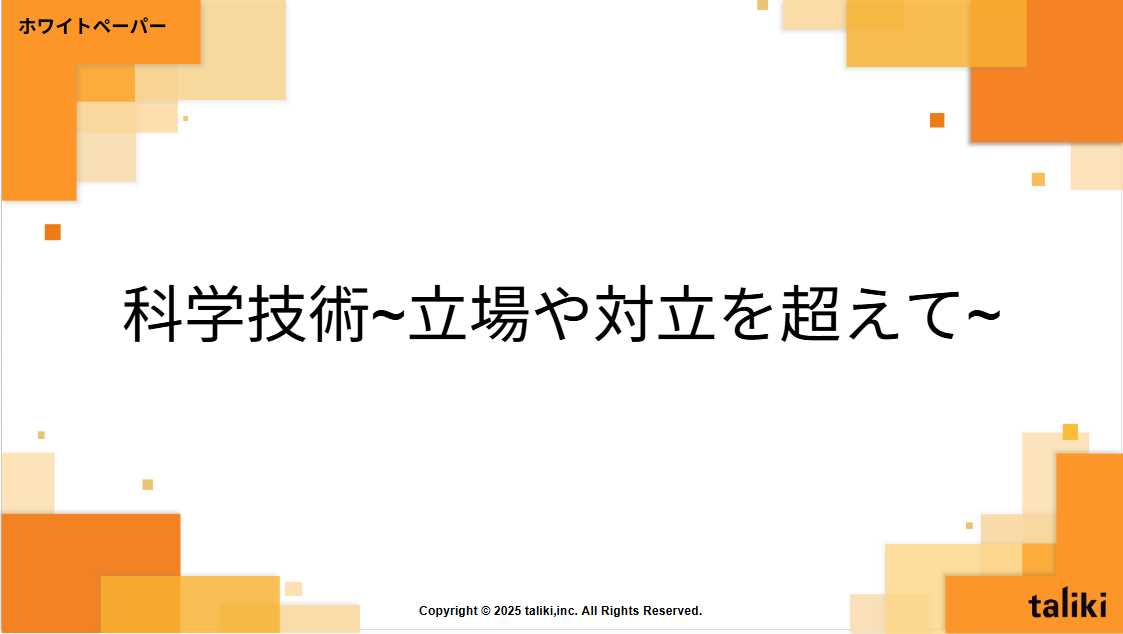それは善い行動なのか?―効果的利他主義の立場から考える社会課題解決の一歩―
もくじ
1. はじめに
社会課題と呼ばれる問題群が日本はもちろん、広く世界に存在している。特にtalikiにおける社会課題とは、「全体最適の歪み」だ。多くの人々にとって都合の良いことを推進した結果、誰かが困るという状況によって生まれた歪みのことを社会課題と定義している。この定義が含む社会課題を例示すると、国内レベルでは貧困、教育・機会格差、フードロス、虐待などが挙げられる。グローバルレベルでは、生物多様性、気候変動、南北格差や開発国における貧困・飢餓、感染症などが挙げられる。このように世界には、国境を超えて地球に大きく横たわるものから、日本に特有のものまで、その性格や特徴が異なる無数の課題が存在している。
では、これらの問題に人類は何をしてきて、どんな変化を生んできたのだろうか。心理学者のスティーブン・ピンカーは、殺人や戦争、貧困など様々なデータを示しながら、30年前と比べて現在、これらの数字が改善していることを明らかにしている。ピンカーはこうしたデータを示しながら世界は確実に良くなっており、さらにこの歩みを進めることの意義を強調する。
しかし、それでもなお、世界では戦争や虐殺、民族弾圧などの国家による暴力に苦しむ人々や、人身売買や強制結婚、性器切除などの著しい人権侵害、気候変動の影響による気候難民の発生など、辛く苦しい現実に直面する人々が多く存在する。
人類はさらにこの社会、世界をよりよくするために何ができるだろうか。本ペーパーでは「いちばんたくさんのいいこと」(Singer 2016)を個人や組織が様々な領域で実践することによって、あらゆるアクターが社会課題解決の推進者として解決に取り組む社会を提案する。
なお、本ペーパーは会社の公式見解ではなく個人の見解です。本論は、あくまでも1案であり、これを読んでいただいた方が、自身と社会と向き合うきっかけとなることを願っています。
2. 社会課題の解決は進んでいるのか
本章では、社会課題と呼ばれるものの解決が進んでいるのか、あるいはそうではないのか、その全体像を理解する。
まず、課題の解決が進んでいる領域として、貧困と平均寿命を取り上げ、この数十年でどの程度解決が進んでいるのかを理解する。次に、今後その解決を進めるべき領域として、気候変動、難民を取り上げる。
2-1. 解決が進んでいる領域
本節では解決が進んでいる領域として、貧困と平均寿命に注目する。この両者は様々な国際機関によって問題視され、資金的・人的など様々な支援が行われてきた。
2-1-1. 貧困
貧困は地球規模の課題の代表的なものの1つと言っても過言ではない。この問題に取り組む国際組織の1つである世界銀行によれば、1日2.15ドル未満でくらす人々を「極度の貧困層」と定義し、このレベルの貧困にある人々の生活改善に向けた取り組みが進められている。世界銀行は貧困削減の取り組みについて、次のように分析を行っている。
(中略)過去30年間の貧困削減の傾向を探りました。その結果、新基準でもやはり、1990年以降、貧困削減は目覚ましく進展していると言えますが、近年そのペースは落ちています。新基準に照らすと、極度の貧困は、サブサハラ・アフリカをのぞくすべての地域でわずかながら増加しています(世界銀行2025)。
実際に、2021年に改定された国際貧困ラインで世界における極度の貧困層の人口を見ると次のようになる。特に1998年以降、極度の貧困状態にある人々の人口が急速に減少していき、2010年代には1990年代後半の3分の1程度にまで減っていることが分かる(図1、2)。
図1:世界における極度の貧困状態にある人口(World Bank)
図2:世界における貧困状態にある人口(中低所得国平均)(Wold Bank)
図3:世界における貧困状態にある人口(高位中所得国平均)(Wold Bank)
※図は文末のPDF版よりご確認ください。
しかし、その一方で、中低所得国平均である3.20ドルライン(図2)や、高位中所得国平均である5.50ドルライン(図3)では、貧困状態にある人の数は増加する。このことから、世界における貧困は未だ完全に「解決した」と言うことはもちろんできないが、その解決のために世界レベルで取り組みが進められ、その結果として上述のように確かにその解決が進められている問題であると言える。
2-1-2. 平均寿命
平均寿命は世界における医療資源の状況、医療サービスへのアクセシビリティの状況など、人が置かれた医療に関わる環境を理解する上で重要な指標である。ここでは世界において平均寿命がどのように推移していったのかを確認する。
国際通貨基金が発行する一人あたりGDPの世界ランキングをもとに、ワースト5の国であるブルンジ(BI)、南スーダン(SS)、マラウイ(MW)、イエメン(YE)、中央アフリカ(CA)の平均寿命を表したグラフが以下である(図4)。この5カ国の平均寿命は63歳であり、世界平均である73歳よりも10歳ほど短い。
図4)ブルンジ・南スーダン・マラウイ・イエメン・中央アフリカにおける平均寿命の推移(World Bank)
※図は文末のPDF版よりご確認ください。
緑の線で示した南スーダンと濃い青で示した中央アフリカ共和国では内戦などの情勢不安が影響し、他3カ国とは異なった推移の仕方をしているが、平均寿命が伸びている傾向にあることは理解することができる。一方の世界平均は次のようになっている(図5)。
図5)世界の平均寿命の推移(World Bank)
※図は文末のPDF版よりご確認ください。
伸びているのは平均寿命だけではない。乳幼児死亡率も世界レベルで低下し、健康寿命も伸びている。このように、世界レベルでは平均寿命は伸びており、保健衛生サービスへのアクセシビリティの向上、医療技術の発展、内戦・紛争への介入(e.g. 国連による平和維持活動、選挙支援)など、さまざまな要因からより健康に人が生きることができる環境が整えられている途上にあると言える。
2-2. 解決を進めるべき領域
一方で、これからより強固に取り組むことが求められる領域も存在する。その例が生物多様性、気候変動、難民である。そしてこれら3つの問題はリンクしている。生物多様性は乱獲や開発などの人為的な要因によって種や生息地が減少することによって失われている。その他にも、外来種の持ち込みや里山の放棄による自然の質の低下などによっても生物多様性は失われる。さらに、こうした生物多様性の危機に拍車をかけるのが気候変動である。
気候変動はそれ自体が人類の生存に大きく影響を与える問題であり、気候変動による海水面の上昇、災害の激甚化などは既に大きな被害を与えはじめている。そして気候変動は人類だけでなく、生物多様性とも関連する。例えば、海面温度上昇により、サンゴ礁の白化は深刻な問題になっている。
そして、気候変動は難民も生み出している。「気候難民」と呼ばれ、海水面の上昇や洪水、干ばつによって移住を迫られる人々が2022年だけでも数百万人にのぼっている。
2-2-1. 生物多様性
世界自然保護基金(WWF)が2022年に発表した報告書では、世界中で哺乳類・鳥類・両生類・昆虫類・魚類の個体数は過去50年間で平均約69%減少していることが報告されている。WWFインターナショナル事務局長のマルコ・ランベルティーニ氏はこの数値について、次のように述べている。
この事実は明白であり、重大な警告を発しています。しかも、この数値は、気候変動と自然の危機が相互に関連して深刻な影響をもたらしていることを(中略)私たちがようやく理解し始めた段階で出てきました(WWF 2022: 8)。
同氏が述べたように、世界は2つの危機に直面していると理解することができる。1つは気候変動である。そして、気候変動によって自然環境に影響が生じ、それによって生物多様性の危機という2つ目の危機が生じているのである。
生物多様性は主に3つの多様性のことを指す。1) 生態系の多様性、2)種の多様性、3)遺伝子の多様性の3つである。この3つの次元の多様性は、生物多様性条約によって定義されている(生物多様性センター )。
生物多様性が重要とされるのには大きく2つの要素からなる。1つは生態系サービスの経済的価値であり、もう1つは健康・医療的価値である。
生態系サービスの価値とは、森や海などの環境によって気温や気候の安定を維持したり、災害の被害を小さくするなどの効果によって人類はその恩恵を常に受けている。そうしたある意味、抽象的な恩恵にとどまらず、食料源としての魚や貝、建築資材となる木材や紙、水源など人間の生活の多くはこうした豊かな自然環境に支えられている。そしてこの生態系サービスの恩恵を経済的価値に換算すると、実に1年あたり約33兆ドル(約3040兆円)にのぼる(国際自然保護連合試算)。
生物多様性の健康・医療的価値とは、人類が自然環境から得ている医療的資源のことを指す。医薬品の成分には、約5〜7万種もの植物からもたらされた物質が貢献していることが指摘されている(国際自然保護基金 2019)。さらに、海洋生物から抽出された成分によって作られた抗がん剤は年間で最10億ドルの利益を生み、世界における薬草の取引総額も2001年には430億ドルに到達したとされている(国際自然保護基金 2019)。
このように、生物多様性は人類の生活と切っても切り離せない関係にあり、生態系の保護を進めない合理的な理由はもはやない。
2-2-2. 気候変動
気候変動も生物多様性と並んで人類の生存に大きく影響を与えている問題の1つである。現在の地表の平均温度は、1800年代後半(産業革命以前)と比べて約1.1℃温暖化しており、過去10万年間で最も気温が高くなっている。過去10年間(2011~2020年)は、観測史上最も気温が高い10年となり、過去40年のどの10年をとってみても、1850年以降のどの10年間よりも気温が高くなった。2015年に締結されたパリ協定では、最終的な温暖化を2℃以内に抑えるだけでなく、気温上昇を1.5℃に抑えるために取り組みを進めることが約束されている。そのためには二酸化炭素排出量を大きく削減することが必要不可欠であり、そうでなければ気温は2100年までに3℃上昇し、人類の生活に甚大な影響を与えかねない状況になる。
気候変動への危機感は2019年、国連のグテーレス事務総長は、気候変動はもはや気候緊急事態であるとしたことにも表れている。さらに、英国紙The Guradianなどのメディアでも気候変動(climate change)に代わり気候危機(climate crisis)や気候緊急事態(climate emergency)などの語が用いられるほどになっている。このように、気候変動は危機的な状況にあり、その解決が急がれている状況にあるが、先進国と開発国の対立、各国の国内状況や国際政治的な状況によってその解決に対して世界レベルでも各国レベルでもまだまだ対応が遅れているのが現状である。
気候変動が進むとどのような影響が発生するのだろうか。大きくは食料・水不足、災害の激甚化、紛争の増加の3つを指摘することができる。
気候変動により海水面が上昇することで、最大で約5億人が侵食の影響を受けると試算されている。そしてその結果、全体の約30%もの食料が失われると予測されている。さらに、水質の悪化や水源の枯渇などで水資源のアクセシビリティが低下するなどし、食料・水不足が懸念されている。
災害の激甚化も気候変動がもたらす影響の1つとして懸念されている。熱波や干ばつ、台風、ハリケーンは全世界で猛威を振るっており、災害の90%が気象・気候関連とみなされるまでに至っている。災害による世界経済への損害は毎年5,200億米ドルに上るほか、その結果として2,600万人が貧困に追いやられていると考えられている。
さらに、気候変動が紛争を誘発する可能性もある。上述のように、気候変動が食料や水不足、居住可能な土地の減少を招き始めている。こうした資源の減少が獲得競争を激化させ、社会経済的な緊張を高め、最悪の場合紛争の発生も考えられる。
こうしたように、気候変動の影響は単に気温が上昇するだけにとどまらず、生命の維持に直結する問題である。
2-2-3. 難民
前述したような気候難民に限らず、難民も現代社会における大きな課題の1つである。
2024年までの過去30年間の難民の数を示したのが以下のグラフである(図6)。グラフを見ると、2011年を境に、増加傾向が続いていることが分かる。
図6:30年間の難民の数(UNHCR)
※図は文末のPDF版よりご確認ください。
2025年の最新データでは、世界で約1億2210万人(UNHCR 2025)が故郷を追われている。主な要因としては、スーダン、ミャンマー、ウクライナにおける紛争及び戦争が挙げられる。国別に見ると、スーダンが最多で1430万人にのぼっている(難民および国内避難民)。次いでシリアで1350万人、アフガニスタンで1030万人、ウクライナで880万人となっている。
さらに、UNHCRが公表したレポートでは、難民の約7割が近隣諸国への避難であり、また難民の7割以上が低中所得国で受け入れられている。世界で最も難民を受け入れているのは実に全体の8分の1を受け入れているレバノンである。
一方で、支援を行うUNHCRの資金は2025年までの10年間、ほとんど増えていない。UNHCRのグランディ高等弁務官は次のように語っている。
資金削減が続く厳しい状況のなかでも、この半年の間に、希望の光も見えています。10年以上にわたる避難生活を経て、200万人近くのシリア人が故郷に戻ることができました。ただ、シリア国内はいまだに脆弱であり、生活を再建するには私たちの支援が必要です(UNHCR駐日事務所 2025)。
支援すべき人の数が増加しているのにも関わらず、資金の相対的な減少により、充分な支援が行えていない現状がある。まずは何よりも、外交および国際的な協力による内戦や戦争の停止によって強制移住を迫られる人々の数を減らす努力が必要である。しかし、停戦までや停戦以降も安全で健康な環境の構築支援や医療支援は必要であり、UNHCRに代表される国際的な難民支援組織は必要不可欠である。
2-3 まとめ
本章では、社会課題の解決は進んでいるのかという問題意識のもと、解決が進んでいる領域として貧困と平均寿命を取り上げた。どちらも60年前とは比較にならないほどに改善している。これは諸テクノロジーや医療技術の発展といった工業的な要素だけではなく、世界銀行や国際通貨基金、世界保健機関などの国際組織をはじめとした様々なレベルの非政府組織の様々なリソースの投下であることは間違いない。つまり、問題設定を適切に行い、リソースを集約し、透過することができるならば、問題は解決に向けて大きく動き出せるということが言えるだろう。
一方で、本章後半では未だ解決が進んでいない領域として、生物多様性、気候変動、難民を取り上げた。特に生物多様性や気候変動については、比較的新興領域の問題であるという反論は可能だろう。しかしながらこの3領域がリンクしながら、それぞれの問題が深刻化していることを考えれば、こうした問題が問題として国際社会において広く認知され、問題解決に向けた動きを加速させていく必要がある。
では我々、個人には何ができるのだろうか。次章ではその実践の方法について検討を進めていく。
3. どのように社会課題の解決を進めていくべきか?
本章では、前章で確認したような社会課題の解決を進めていくためのアイデアとして、効果的利他主義(以下EA)を取り上げる。まず1節で社会課題解決のための考え方として効果的利他主義の有効性を検討する。
2節では効果的利他主義の内容について確認し、3節でその問題点を整理する。その上で4節では、そうした批判を乗り越え、よりよいコンセプトとしての「修正効果的利他主義」を提案する。
3-1. 効果的利他主義の提案
社会課題解決を推進するための考え方として効果的利他主義(Effective Altruism)を導入することを提案したい。EAとは利他主義の中でもその効果、より分かりやすく言えば、「インパクト」を重視する利他主義の実践形式の1つである。
社会課題解決をさらに力強く推進するためには、少なくとも個人(individual)レベルと集団(collective)レベルでその効果を検証しつつ、インパクトが最大化される解決策により多くのリソースが投下される必要がある。
世界にある資源は有限であり、この制約の中で効果を最大化するためには、闇雲に利他行動を実践するのではなく、その行動が持つインパクトを定量的、定性的に分析し、インパクトが最大化される異なる選択肢があるならば、それを実行することが社会課題解決の推進、加速につながるからだ。
3-2. 効果的利他主義とは何か
EAを一言で言い表すと、「自分の幸福よりも他者の幸福を優先する利他主義を、自分が今持つ資源を最も効果的な選択肢に投資することによって実践する考え方」と言うことができる。より簡単には、「利他主義を最も効果的な形で実践すること」とも言えるだろう。以降ではまず利他主義の考え方について触れた上で、EAの概観を記述する。
EAの定義について、その旗手であり『〈効果的な利他主義〉宣言!』の著者であるウィリアム・マッカスキルは次のように述べる。
〈効果的な利他主義〉は「効果的」と「利他主義」というふたつの要素からなる。(中略)私が使う「利他主義」という言葉は、単純にほかの人々の生活を向上させるという意味だ。(中略)もうひとつの要素は「効果的」という部分だ。これは手持ちの原資でできるかぎりのよいことを行なうという意味だ。効果的な利他主義では、単に世界をよりよくするとか、ある程度よいことを行なうのではなく、できるかぎりの影響を及ぼそうとする(MacAskill 2015=2018)。
EAのポイントは利他主義を「へりくだった自己犠牲ではなく、隠された動機を必要とすることなく他者の利益を考慮して自発的に行為しようとすること」(Nagel 1970=2024: 117)ではなく、他の人々の生活を向上させるというように単純に理解することである。よりよい社会、地球のために自己が有する資源をどのように(どこに)投資することで最も費用対効果が得られるかという帰結主義の立場を取る(竹下・清水 2024)。
EAはもともと、米国の金融エリートらによって、どのNGOに寄付をするとその寄付の効果が最大化されるのかという議論にその起源を持つ。故にどれだけよくしたいと考えているのかや直接的な行動それ自体よりも、自らの持つ資源がどれだけ効率的に使われるのかという点に議論の焦点が当たっている。
3-3. 効果的利他主義への批判
EAには大きく3つの批判点がある。(1)対症療法的、(2)不正義・不平等構造の無視・回避、(3)「効果」の定義の限定性(4)現代世代の(相対的な)軽視、の4点である。
まず1点目の対症療法的であるという批判は、EAが表層の問題解決に注目することから挙げられる批判である。例えば、EAの原則に則れば、「目の前で交通事故があった時、その人を助けるよりも仕事に向かったほうが得られる効果が大きい場合、そちらを優先すべき」と考えられる。つまり、功利計算ならぬインパクト計算によって、その効果がより大きい選択を取ることが推奨されるのがEAである。つまり、本当は目の前の子どもを救うことのほうがより大きな問題の解決につながるとしても、その効果が計算できない以上、今目に見えている問題への対処を目に見えている解決策で実行することがよいことになる。こうした考え方が対症療法的であると批判され、次の論点である不正義や不平等の構造の結果的な無視という批判を招いている。
2点目の不平等構造の無視は上記のような問題構造によって理解することができるだろう。目に見える問題と目に見えるインパクトが重視されるあまり、その奥にある問題構造が軽視されるという批判だ。例えば女性の教育機会の不平等という例について考えてみる。EAの原則に則れば、女性の教育機会拡大に取り組む非営利組織へ寄付することが推奨されるだろう。しかし、その問題が女性の教育に制限をかけることを推進する政府によって引き起こされている場合、本当に何か手を付けるべきはそうした国家のあり方自体だろう。しかし、これは価値・文化的な差異や多国家間による議論であり、必ずしもその対策へ乗り出すことが1つ2つの非営利組織だけでは不十分だろう。つまり、問題解決のための「トリアージ」が行われているのである。このようにして、プールに大きな穴が空いていることを理解しながら、流れ出る水をバケツで汲むような対策が取られているという批判がなされている。
3点目の批判は前述のトリアージとも関連し、「効果」が指し示すものが限定的であるという批判である。今までも既に確認してきたように、ここで想定されている「効果」とは費用対効果と言っても問題ないだろう。後述のようにEAの実践の手段として推奨されるのはお金を稼ぐことであり、収入のいくらかを寄付することである。
これでは社会的にハイインパクトの活動を実践してもその効果は正しく評価することはできない。しかしその一方で、「全てのことに意味がある」などと肯定すると、本来は効果が乏しい対策であっても、正当な批判のロジックを失うことになる。このように、EAにおける効果をどのように定義するのかという点については批判がなされている。
4点目の批判は現代世代の相対的な軽視である。これはマッカスキルが提唱するもう1つの概念である「長期主義(Longtermism)」と関連してなされる批判で、未来世代のためによいことを実践することによって、相対的に現在を生きる世代の相対的な軽視、透明化を招きかねないというものである。
3-4. 修正効果的利他主義(Social Effective Altruism)の提案
3-3で確認してきたように、EAにはいくつかの批判点が存在する。そしてそのどれもが的を得たもののように考えられる。そこで本稿では、それらの批判を採用し、EAのアップデートを提案する。
まずは「効果的」の定義を拡張することを提案する。数値的インパクトのみを効果の対象とするのではなく、その判断が未知数なものについては利他主義を実践することが善であるとする。この点において、「インパクト投資」と呼ばれる投資の考え方とも異なる立場を取る。例えば、インパクト投資を主導する投資家であるロナルド・コーエンはその著書でインパクトは測定可能であり、比較可能なものであると主張する(Cohen 2020=2021)。
一方で、ここで主張する「インパクト」は必ずしも即時的に計測が可能であるものに限定しない。「データ主義」とも呼べる、こうした測定可能なものに焦点を絞ることの欠点は既に指摘されている(Madsbjerg,Rasmussen 2014=2015; Jerry 2018=2019)。計量的なインパクトに限定しないことはEAの従来のコンセプトから大きく外れてしまうだけでなく、計測可能であるにも関わらず、あえて計測せず、感動的なストーリーテリングによってステークホルダーや、課題解決を推進する組織の構成員を説得するような事例も起こる可能性がある。だからこそ、全てのEA的な行いはあらゆる”建設的な”批判に開かれ、説明可能性を負うこととする。これはマルクス・ガブリエルが提唱する「倫理資本主義(ガブリエル 2024)」とも類似する考え方である(※1)。
※1
一方で、マルクス・ガブリエルが『倫理資本主義』において主張する「善」の概念には決定的な問題がある。同書の監修者である斎藤幸平の書評で指摘されている通り(斎藤 2024)、2024年に山陰中央新報社で公開されたインタビューでガブリエルはイスラエル軍によるガザ地区への攻撃について、一般市民を標的にしたものでないとし、ガザ市民の虐殺を否定している(山陰中央新報社 2024)。著者自身によって、彼が主張する普遍的な道徳や倫理観なるものが達成不可能なものであることが示されている。本書においてもガブリエルの主張する「倫理資本主義」というコンセプトを全面的に引き受ける意図はない。
また、その効果が数値的にも未知であるような行いや、反対に計量的なインパクトを最大化することによって犠牲となる世代が生まれてしまうような行為においては、当該世代も保護することもを善い行いとすることで、世代間の不平等を部分的に解消する。
さらに、「対症療法」という批判についても経済合理性それだけで効果を判断するのではなく、むしろ内省的にそれが最も効果的な行為であるのかどうかを反芻し、常に検証の土台に乗せることを重視する。同様に、例えば社会運動の意義についても討議によって判断可能なものとして取り扱うことで「効果」の定義を拡張する。
つまり、修正効果的利他主義(SEA)とは、量的・質的インパクトの双方を「効果」の指し示すものと再定義し、計算合理的なインパクト判断で切り捨てられてしまうような質的なインパクトも量的なものと同様に重視し実践することを善いとするアイデアである。しかし、いずれの場合にも批判は広く開かれ、行為者にはその説明責任がある。この原則を設定することによって効果的という最重要概念のガードレールとすることとする。
4. 個人は効果的利他主義をどう実践できるか?
では、SEAはどのような形で実践可能なのだろうか。ここでは特に個人が実践できることに注目して見ていく。
4-1 Giving Gladlyの実践
Giving Gladly(与える喜び)を養う。効果的利他主義の原初のコンセプトを提唱したピーター・シンガーは、人々は質素に生き、所得の多くを寄付することを主張する(Singer 2015=2015)。しかし、SEAにもとづく個人の実践としては、「Not too frugal, not too laxualy(質素すぎず、贅沢すぎず)」を提案する。
「オキュパイウォールストリート運動(Occupy Wall Street)」が1%の最富裕層に対する99%の抗議であったように、多くの人々が質素に生きること求められるのはそれによって再配分の歪みに関する問題を覆い隠してしまうことになりかねない。
そこで考えたいのが「Not too frugal, not too laxualy(質素すぎず、贅沢すぎず)」である。健康で、文化的である程度の豊かさはすべての人が享受できるべきである。しかし、過度な贅沢や消費による快楽の享受は本来的には健康的でも文化的でもなく、むしろ巨大資本による収奪に他ならない。だからこそ、「それなりの」豊かさを享受し、その上で余剰が生じた場合にはその余剰を寄付や、SEAの原則に則した行動に使うことを推奨したい。
やはりここでも批判可能性と説明責任は重要であるので、修正効果的利他主義を実践するための個人的な宣言のようなものをインターネット上で公開することも考えられるだろう。
4-2 お金を稼ぐ
もっともシンプルであるが、お金を稼ぐことはEAではもちろん、SEAにおいても実践のための重要な方法の1つである。しかし、お金を稼ぐこと自体に抵抗感を抱く人も少なくないだろう。ここで1つ思考実験を行う。
ある時、あなたがソーシャルメディアを見ていると、国際機関による難民支援の広告が流れてきた。その広告では数値的なインパクトと上手く練られたストーリーテリングで被害の深刻さと寄付の実践のインパクトを伝えてきた。ここであなたには大きく2つの選択肢がある。1)それを引用し、シェアすること、2)その国際機関に毎月一定額を寄付することである。どちらを選ぶべきだろうか。
この問題に対する最もシンプルかつ、SEAの原則に則った回答はその両者を実践することである。EA及びSEAが最も重視するのはGiving Gladly、すなわち与える喜びの実践である。つまり、自分の持つリソース、特にお金を投下することが最も基本的で根本的な効果的利他主義の実践の方法である。
自らに充分な金銭的な余裕が存在しなければ、SEAの実践は困難になる。SEAの実践という手段による世界に横たわる課題の解決という目標の達成のために何よりも欠かせないのは個人によるSEAの実践だ。そしてそのSEAを実践するためには金銭的な余裕があることは重要だろう。だからこそ、善いことのためにお金を稼ぐことは本来、妨げられるべきではない。類似した議論は日本におけるNPO職員の待遇を巡る議論にも同様のことが指摘できるだろう。
しかし、ただお金を稼げというのではあまりにも倫理観に欠けているように思う。過労死が日本のみならず世界的な問題になりつつある状況を考えれば、大事にすべきは「お金は大事、健康はより大事」という原則の中で均衡点にある仕事をすることだろう。
4-3 旗振り役になる/官僚になる/研究者になる/社会起業家になる
SEAを実践することはGiving Gladlyを実践し、お金を稼いで寄付をすることだけではない。プレイヤーや第三者的に助言をするような役割を担う人々の存在も不可欠だ。
寄付に限らないSEAの実践として、SEAの旗振り役になること、官僚になること、研究者になること、そして社会起業家になることも選択肢に上がるだろう。1つ1つについて詳説することはしないが、寄付をするためには寄付先となる組織が必要であり、当然その組織で働く人や、その組織のインパクトをチェックし、助言するような研究者や、組織を立ち上げる社会起業家や、そもそもSEAという考え方を広める人の存在も重要になってくるだろう。
4-4 まとめ
しかし、いずれの場合においても考慮すべきことは、そのロールが自らにとって最も効果的であるかという点であるだろう。あらゆる人がある特定の職業に向いているとは言えないのと同様に、個々人によって最も効果的に善い行いを実践できる方法は違うはずである。少し長いが、マッカスキルの主張を以下に引用する。
どうすれば最大限に人々の役に立てるのか?それをじっくり考えれば、今までより少しだけよいことではなく、桁違いによいことができる。
ひとりの人命を救うところを想像してほしい。炎上する建物に飛び込み、ドアを蹴破り、煙や炎のなかを突き進んで、幼い子どもを安全な場所まで引きずり出す。もしそんなことをすれば、一生の勲章になるだろう。それが数人の命ならどうだろうか。ある週は燃え盛る建物に飛びこみ、次の週は溺れかけている人を助け、その次の週は銃で打たれようとしている人をかばったら?きっと選ばれし人生を送っている気分になるだろう。ニュースになり、ヒーロー扱いされるにちがいない。
しかし、私たちはそれよりはるかにすばらしいことができる。
もっとも厳密な推定によると、発展途上国でひとつの命を救うのにかかる費用はおよそ3400ドル(1QALYあたり100ドル)だ。これは、富裕国の大半の人々ならほぼ同じ生活水準を保ちながら毎年寄付できるくらいの金額だ。やろうと思えば、生涯でたったひとつの命ではなく、働くあいだ毎年ひとつずつの命を救うことだってできるのだ。慈善団体に寄付するのは、燃え盛る建物のドアを蹴破るのと比べれば確かに地味な行動だが、それに匹敵する価値がある。もっとも効果的な慈善団体に寄付をするという単純な行為ひとつで、何十人という命を救える。すばらしいとは思わないだろうか?(MacAskill 2015=2018: 55)
これは、炎上する建物の中に命を救うために突入する消防士の行為に意味がないと主張しているわけではないことをまずは確認しておきたい。そしてその上で、自身にそのケイパビリティがある限りにおいて、SEAの原則から言えば、炎の中に入り、人命を救うことも効果的な利他主義の実践であるだろう。しかし、ここで問われているのは、自身が持つあらゆるリソース、ケイパビリティを最大化した善い行いは今行っていることだろうか?という視点である。そうした意味で、寄付者として実践するのか、あるいは課題の最前線で汗を流すのか、あるいはそうした政策の立案者になるべきなのか、さまざまな選択肢の中で効果を考えた上で決断することが重要であるだろう。
5. おわりに
このペーパーでは、効果的利他主義(EA)、そして修正効果的利他主義(SEA)の立場から、諸個人が最も効果的な善い行いを推進することで社会課題の解決は可能であるだろうという、楽観主義的な立場から論点を提起した。SEAが批判に開かれ、また行為者は説明責任を負うべきであるという主張をしたのと同様に、このペーパー自体も批判に開かれ、著者はその説明責任を負うことをここに明記する。
その上で、より詳細に著者の立場を明らかにしたい。それは、あらゆる慈善活動や社会貢献活動等、営利・非営利を問わずそうした性格を持つ活動を批判し、否定するものではないということである。これは効果的利他主義それ自体の議論がはらむ問題であるが、決して冷笑的な立場を取るものではない。むしろ、特に日本においてはより多くの人々が寄付という文化に慣れ親しみ、より多くの資金がNGOやNPOに流れるべきであるという立場である。
しかしその一方で、営利・非営利を問わず、そのインパクトが集団レベルでも、個人レベルでも問われるべきであると考える。個人レベルでも組織レベルでも、その役割が自らの持つリソースの効果を最大化した状態であるのかは問われるべきであるし、ある意味では批判に対して開かれ、そうした批判に対する説明の責任を負うべきであるだろう。「善いことをしている」というナラティブにとらわれず、時にはさまざまな計測可能な数値を示し、時には質的なデータを用いて批判に応答し、自らの持つミッションの重要性を積極的に示すべきだろう。そうした行動自体が他者がSEAに共鳴するきっかけになり得ると考える。
このペーパーは2025年に開催されるソーシャルカンファレンス「BEYOND2025」に先立って公開され、アジェンダを提起することがその目的である。「再分配」とはその用語の文脈になぞらえれば本来は政策や国家の在り方として議論されてきた。国家による再分配が問題となるたびに、福祉国家や社会的投資国家は姿を変えながらよりよい再分配の実践を模索し続けている。少なくとも著者は再分配が起こっていないとは考えていないが、再分配に関する問題が提起されること自体には意義があると考える。
また、富む者が主体的に自らのリソースを他者に投下する行為、つまり寄付は日本においてはもう少し考えられてもよいテーマだろう。あらゆる活動に国家が介入するのではなく、ある意味で自助的、相互扶助的なアイデアが推進されてもよいはずだ。そうした観点から、現在の社会の問題、そしてあるべき社会を考える材料の1つとして本ペーパーが役立てば幸いである。
参考文献
Cohen Ronald, 2020, IMPACT Reshaping Capitalism to Drive Real Change, Ebury Pr.(斎藤聖美訳, 2021, 『インパクト投資―社会を良くする資本主義を目指して―』日本経済新聞出版.)
Donna Barne, Divyanshi Wadhwa, 2019, Year in Review: 2019 in 14 Charts, World Bank(2025年8月22日取得, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/12/20/year-in-review-2019-in-charts).
福富満久, 2025, 『国際正義論』東信堂.
ガブリエル・マルクス, 斎藤幸平監修, 土方奈美訳, 2024, 『倫理資本主義の時代』早川書房.
井上達夫, 2014, 『世界正義論』筑摩書房.
Iason Gabriel, 2015, “Response to Effective Altruism,” BOSTON 50 REVIEW, (2025年8月22日取得, https://www.bostonreview.net/forum/peter-singer-logic-effective-altruism/response-iason-gabriel/).
IMF, 2025, “GDP per capita, current prices, ” World Economic Outlook, (2025年8月22日取得, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.)
環境省, 「生物多様性に迫る危機」生物多様性, (2025年8月22日取得, https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/biodiv_crisis.html.)
国際連合広報センター, 「気候危機―勝てる競争」『国際連合広報センター』(2025年8月22日取得, https://www.unic.or.jp/activities/international_observances/un75/issue-briefs/climate-crisis-race-we-can-win/.)
Madsbjerg Christian, Rasmussen B. Mikkel, 2014, The Moment of Clarity: Using the Human Sciences to Solve Your Toughest Business Problems, Harvard Business Review Press.(田沢恭子訳, 2015, 『なぜデータ主義は失敗するのか?―人文科学的思考のすすめ―』早川書房.)
Mathew Snow, 2015, “Against Charity,” JACOBIN, (2025年8月22日取得, https://jacobin.com/2015/08/peter-singer-charity-effective-altruism/).
MacAskill William, 2015, DOING GOOD BETTER, Avery.(千葉敏生訳, 2018, 『〈効果的な利他主義〉宣言!―慈善活動への科学的アプローチ―』みすず書房.)
――――, 2024, 『見えない未来を変える「いま」―〈長期主義〉倫理学のフレームワーク―』みすず書房.
――――, 2024, 『我々は歴史の蝶番に生きているのだろうか?』「現代思想2024年8月号 特集=長期主義」青土社.
Mahler Gerszon Daniel et al,, 2022, “How do the 2017 PPPs change our understanding of global and regional poverty?,” World Bank Blogs, (2025年8月22日取得, https://blogs.worldbank.org/en/opendata/how-do-2017-ppps-change-our-understanding-global-and-regional-poverty.)
Muller Z. Jerry, 2018, The Tyranny of Metrics, Princeton University Press(松本裕訳, 2019, 『測りすぎ―なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?―』みすず書房.)
Nagel Thomas, 1970, The Possibility of Altruism, Princeton University Press.(蔵田伸雄訳, 2024, 『利他主義の可能性』勁草書房.)
Pinker Steven, 2018, Enlightenment Now, Viking.(橘明美・坂田雪子訳, 2019, 『21世紀の啓蒙』草思社.)
斎藤幸平, 2024, 「哲学者と子どもたちによる資本主義の改革は実現可能か? マルクス・ガブリエル『倫理資本主義の時代』書評」『Hayakawa Books & Magazines(β)』(2025年8月22日取得, https://www.hayakawabooks.com/n/n42e9e187b450?sub_rt=share_h.)
山陰中央新報社, 2024, 「ガザでの虐殺 反ユダヤ主義復活に警戒 独哲学者、ボン大教授 マルクス・ガブリエル」『山陰中央新報デジタル』(2025年8月22日取得, https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/513169.)
Singer Peter, 2015, THE MOST GOOD YOU CAN DO, Yale University Press. (関美和訳, 2015, 『あなたが世界のためにできるたったひとつのこと』NHK出版.)
生物多様性センター, 「生物多様性条約」環境省, (2025年8月22日取得, https://www.biodic.go.jp/biolaw/jo_hon.html.)
世界銀行, 2025, 「世界の貧困に関するデータ」世界銀行, (2025年8月22日取得, https://www.worldbank.org/ja/news/feature/2014/01/08/open-data-poverty.)
竹下昌志, 清水颯, 2024, 「効果的利他主義は道徳的義務なのか?―帰結主義とカント的観点からの正当化―」『Contemporary and Applied Philosophy』15: 135-171.
UNHCR, 2025a, “Number of people uprooted by war at shocking, decade-high levels,” UNHCR, (2025年8月22日取得, https://www.unhcr.org/news/press-releases/number-people-uprooted-war-shocking-decade-high-levels-unhcr.)
――――, 2025b, GLOBAL TRENDS FORCED DISPLACEMENT IN 2024, (2025年8月22日取得, https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024.)
UNHCR駐日事務所, 「数字で見る難民情勢」UNHCR日本, (2025年8月22日取得, https://www.unhcr.org/jp/global-trends-2024.)
――――, 2025, 「UNHCR、紛争で故郷を追われた人の数が、過去10年で衝撃的な高水準に達したと発表」UNHCR日本,(2025年8月22日取得, https://www.unhcr.org/jp/pr-250612).
World Bank, Poverty and Inequality Platform (2025年8月22日取得, https://pip.worldbank.org/home).
World Bank, “Life expectancy at birth, total (years),” World Bank Open Data, (2025年8月22日取得, https://data.worldbank.org/).
WWFジャパン, 2019, 「生物多様性とは?その重要性と保全について」WWFジャパン公式サイト (2025年8月22日取得, https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3517.html.)
――――, 2022, 『生きている地球レポート2022』 (2025年8月22日取得, https://www.wwf.or.jp/activities/data/20221013lpr_02.pdf.)
本レポート・記事は転載禁止です。ご希望の方はこちらよりPDF版をダウンロードいただけます。
執筆
上野裕太郎
taliki シンクタンク事業部 リサーチャー
中澤 舟
taliki シンクタンク事業部 リサーチャー
関連する記事
社会課題に取り組む起業家のこだわりを届ける。
ソーシャルビジネスの最新情報が届くtalikiのメルマガに登録しませんか?